湯島天神
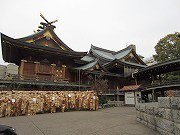 湯島天神(湯島天満宮)は、東京都文京区の、東京メトロ千代田線の湯島駅より東へ徒歩2分(東京メトロ銀座線の上野広小路駅からは徒歩5分の地に位置する鎮守社。
湯島天神(湯島天満宮)は、東京都文京区の、東京メトロ千代田線の湯島駅より東へ徒歩2分(東京メトロ銀座線の上野広小路駅からは徒歩5分の地に位置する鎮守社。
戦前の社格は東京府(東京都)の府社に列し、現在は神社本庁の別表神社となっている。
雄略天皇2年(西暦458年)に勅命で天手力雄命を祀って創建され、正平10年(1355年)に住民が菅原道真を合祀。文明10年に太田道灌が再興した。
なお、江戸期の地誌では、文明10年夏に太田道灌が江戸城内に勧請し秋に湯島に社を建てた、あるいはその前段に正平10年に民が勧請した、とするものが多い。


銅鳥居は江戸前期の1667年建立。東京都指定有形文化財。


社殿は平成7年建立。拝殿・幣殿・本殿を連結した権現造。

絵馬殿は明治25年建立。
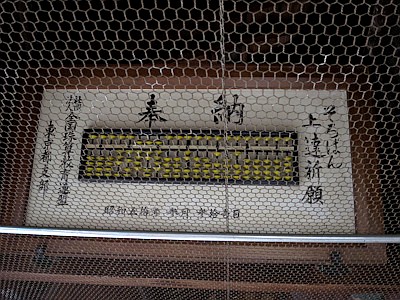



摂社戸隠神社は地主神。


天三火伏稲荷神社は、かつては備中庭瀬藩主板倉邸の鬼門除けの稲荷であった。覆屋の屋根を支える支柱に鳥居を組み込んである。

境内は高台にある。江戸時代、庶民は境内からの見晴らしを楽しんだ。

東参道には、坂の緩やかな女坂と、急な男坂がある。

年中行事
初詣
湯島天神への初詣の参拝客は多く、露店も割りと出る。下の写真は元日の昼と夜の様子。


節分豆まき

梅まつり
境内には白梅を中心に梅が植えられており、2月中旬~3月中旬には梅まつりが開かれる。この行事に関する詳細は「湯島天神 梅まつり」の記事を参照。

例大祭
当社の例大祭は5月下旬。隔年で鳳輦と台車に乗せた宮神輿が渡御する。これとは別に、4年ごとに宮神輿が担がれて渡御し、その中間年には町神輿の連合渡御が行なわれる。この行事に関する詳細は「湯島天神 例大祭」の記事を参照。


菊まつり
11月頃に開かれる菊まつりは、約二千株が出展される、比較的大規模なもの。この行事に関する詳細は「湯島天神 菊まつり」の記事を参照。

近隣には上野公園、旧岩崎邸庭園、教証寺、講安寺、麟祥院、横山大観記念館、東大本郷・弥生キャンパスなどがある。











